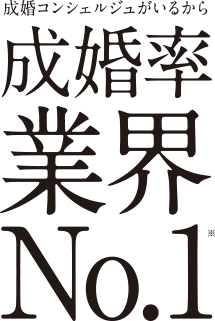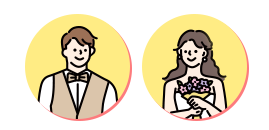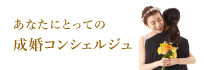輪中の郷
輪中の郷について
輪中の郷は三重県桑名市にある、輪中をテーマとした博物館類似施設です。輪中とは水害から集落を守るために堤防で周囲を囲んだところを指し、岐阜県南部と三重県北部または愛知県西部の県境にある木曽川と長良川、 揖斐川からなる木曽三川とその支流の、扇状になった河口部にあった所が有名です。木曽三川の流域では古くから洪水と闘ってきました。川の高さの方が堤防の中よりも高くなっている天井川と呼ばれるもので、 一度洪水が起きると家や耕地などが非常に大きな被害を被ってしまうのです。伊勢湾台風では5千人以上の死者や行方不明者が出ました。さらに輪中は盆の様な形になっているので、水がなかなか引いていかないという特徴もあり、被害もより大きくなってしまいます。 木曽三川が作ったたくさんの中州に人が住むようになったのは鎌倉時代のことで、その時に堤防が作られました。それらの堤防が輪のようで、輪の中に住むような形だったことから輪中と呼ばれるようになりましが、堤防ができたことで川の底が高くなり、 さらに洪水の被害が増えるようになったのです。雪解けの頃や大雨が降ると洪水が起こります。江戸幕府が洪水を防ぐために薩摩藩に命じて工事をさせたのですが、 幕府は木曾川の西岸を東岸よりも低くするように命じたため徳川御三家の領地である東野尾張地区だけ洪水から守られましたが、西側の美濃側の洪水はさらに多くなってしまいました。 そのためどの地域も完全に洪水を防げるようになることが輪中に住む人たちの願いで、それが実現したのは明治35年、1903年のことでした。 オランダ人のケレップという技士の指導のもと工事が行われ、たくさんの島に分かれていた輪中が一つになって現在の形の輪中となったのです。
輪中の郷でのデート
1993年に設置された輪中の郷では、長島地域の歴史を紹介や民具や絵画などの展示を行っています。歴史民俗資料館とする「アミュージアムエリア」と産業体験館とする「アクティブエリア」があり、 「輪中の暮らし」や「長島からの贈り物」などにちなんだ様々なものが展示されていて、輪中の過去、現在、未来のすべてを満喫することができます。 また館外には、輪中の景観を再現した「アイリススクエア」や「くすの木広場」があります。また様々な農作物を収穫する体験をすることもできます。 歴史や地理などを学ぶことに興味を持つカップルなら、輪中の郷でのデートがおすすめです。付近にはナガシマスパーランドやジャズドリーム、なばなの里など有名なお出かけスポットもあります。 すべてを一日で回ることはできないので、仲が深まったカップルの旅行先として、ナガシマスパーランドのようにアクティブなところと、静かに輪中について学べる輪中の郷のどちらも体験してみるのもよいでしょう。
Pickup Contents
ピックアップコンテンツ
長島駅下車、タクシー(タクシー会社へお迎えの電話必要)で10分。
長島駅発K-バスで17分。
※市内各所からコミュニティバス「K-バス」が運行されています。
(運賃 大人100円)
自動車利用:
東名阪自動車道→長島I.C→(約5分)
国道1号線→押付交差点を北へ・7号→長島IC前交差点右折→(約5分)
台数:50台
※月曜日が祝日の場合は翌日以降の最初の平日が休館日になります
(入館は午後4時まで)
※情報は変更等がございますので、必ずおでかけされる前に公式サイトなどでご確認いただきますようお願いいたします。
料金
※情報は変更等がございますので、必ずおでかけされる前に公式サイトなどでご確認いただきますようお願いいたします。
周辺のデートスポット
紀宝町ウミガメ公園
9:00~17:00
【物産館】
3月~10月 8:30~19:00
11月~2月 8:30~18:00
その他のエリアを見る
タメニーグループのサービスサイト
- セキュリティ・CS向上への取組み
- 個人情報保護方針
- 個人情報の取扱いについて
- 情報セキュリティ基本方針
- 品質方針
- 苦情対応方針
- 一般事業主行動計画
- 著作権・リンクについて
- ソーシャルメディアポリシー
- 履歴情報および特性情報の利用等について
- 特定商取引法に基づく表記
Tameny Inc. All rights Reserved.