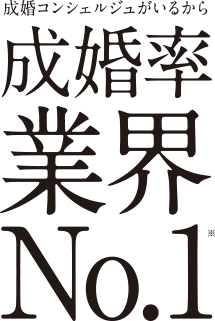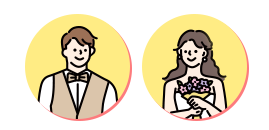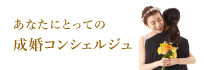清水園
清水園ってどういうところ?
新潟県新発田市にある清水園は、江戸時代の屋敷と庭園の様子を今に伝える場所です。清水園(しみずえん)という名前は、この辺り一帯の地名が「清水谷(しみずだに)」であったことに由来しています。 1666年に建設に着手され1693年に完成した、溝口家の下屋敷を原型としています。溝口家というのは、新発田の地を治めるために、1598年に加賀大聖寺から領地に入った藩祖、溝口秀勝の家系です。 溝口家はその後274年にわたって、新発田藩を治めることになりました。しかし時代が移り変わり、明治時代に入ると屋敷は、沢海村の伊藤家という、越後でも指折りの大地主の所有になります。
そして昭和21年には、財団法人北方文化博物館が管理するところとなり、現代まで至っています。清水園の屋敷が完成した元禄時代は、溝口家の権力はすでに安定していたときです。 新発田藩自体も開発が進み財政は潤っていましたから、元禄時代に盛んになった能楽や茶の湯の文化は、新発田でも楽しまれました。清水園の屋敷と庭園にも、その文化の特徴がよく表れています。 下級武士の生活を垣間見ることができる足軽長屋や、武家屋敷の石黒邸などが園の見どころのひとつですが、外せないのは庭園です。 越後から東北地方にかけては、ほかに類を見ない名園としてその名が知られています。
清水園の入場料は、大人1名で700円です。休園日は1・2月の毎週水曜日と年末年始です。 営業時間は、3月から10月の間は9:00から17:00で、11月から2月までは9:00から16:30までとなります。
清水園でデートをするなら?
清水園をデートコースに入れるのであれば、有名な庭師の作である庭園を散策できるだけの時間は、確保しておきたいところです。 庭の中心に池、周囲には書院を配する形は、池泉廻遊式庭園と呼ばれます。特に清水園の池は、草書体の「水」という文字になっており、デザインに工夫が凝らされています。 この庭園は、もともとは縣宗知(あがたそうち)が造ったものですが、見ることのできる庭園の姿は当時のものではありません。 時代が進むにつれて庭は荒れてしまったため、昭和に入り田中泰阿弥という人物が庭園を修復しました。
田中氏は全国各地の寺院などを請け負った名庭師で、清水園に5つある書院も、すべて田中氏の手によるものです。しかし素晴らしいのは、書院や全体のデザインだけではありません。 庭石や地面を覆う苔も非常に美しく、なんだか自然と寄り添って歩きたくなってしまうような、神秘的な雰囲気に溢れています。 付き合ってから長いカップルも、まだ日が浅くてぎこちないカップルも、食事デートの前に是非この庭園を訪れてみましょう。 2人の距離も縮まり、そのあとの食事のあいだも良い雰囲気で過ごせそうです。
Pickup Contents
ピックアップコンテンツ
所在地
白新線・羽越線 JR新発田駅より徒歩10分
自動車:
日本海沿岸東北自動車道 聖籠新発田インターより約15分
台数:約50台
11月~3月(9:00~16:30)
※情報は変更等がございますので、必ずおでかけされる前に公式サイトなどでご確認いただきますようお願いいたします。
料金
20名以上団体料金 大人600円 子供250円
※情報は変更等がございますので、必ずおでかけされる前に公式サイトなどでご確認いただきますようお願いいたします。
周辺のデートスポット
三条鍛冶道場
体験希望の方は午後3時30分までに受付をしてください。
・祝日の場合は翌日
・臨時休館日は12/29~1/3
佐渡太鼓体験交流館(たたこう館)
その他のエリアを見る
タメニーグループのサービスサイト
- セキュリティ・CS向上への取組み
- 個人情報保護方針
- 個人情報の取扱いについて
- 情報セキュリティ基本方針
- 品質方針
- 苦情対応方針
- 一般事業主行動計画
- 著作権・リンクについて
- ソーシャルメディアポリシー
- 履歴情報および特性情報の利用等について
- 特定商取引法に基づく表記
Tameny Inc. All rights Reserved.